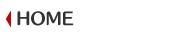市議団だより−議会&市政の報告
【09.02.28】根本市議が一般質問をおこないました
就学援助制度をすべての学年に周知することを検討
 根本みはる市議の一般質問の内容はつぎのとおりです。
根本みはる市議の一般質問の内容はつぎのとおりです。
○子どもの豊かな育ちを保障する「子ども総合計画」の策定にあたり、市として、どんな体制でつくるのか を聞き、「豊田市こども条例」の理念に基づいてつくることを市の答弁として確認しました。
①21年度取り組む具体的施策は「妊産婦健診を14回にくわえ、産後も1回を無料に。おめでとう訪問を市内全域に拡大し、86人の母子保健推進員が1800の家庭を訪問する。3歳児の保育要件の拡大をす る。」という答弁がありました。それに対して、「妊産婦健診の無料回数を拡大するという点は、日本共産党市議団が、その施策拡大を議会で求め続けてきた結果であること。」また、「3歳児保育要件の緩和は、昨年、市民団体から要望書として出されていたものであり、その一部が反映されたもの」として、評価をしつつ、今後施策に反映することを意見として述べました。
②また、計画策定にあたり、住民の意見を幅広く聴取し、反映させるために、構成メンバーを市民から公募することや、協議会の傍聴にこられた方々の意見を反映させるしくみを作ることを確認しました。
大項目2として
深刻な雇用悪化のなかで、子どもの健やかな成長を第一に考えて、学校と行政で子どもと家庭にどんな支援が必要なのかを問いました。
①子どもや家庭への現在の相談体制、外国人家庭への相談体制についての質問に、
「全小学校を対象とした相談の体制として、中学校に配置しているスクールカウンセラーあらたに2名増員し、学校コンサルタントを1名増やし4名の体制にする。」外国人家庭へは「巡回指導員、日本語指導員が対応。学校では生活指導を行い、校外では担任とが家庭訪問をする。」と答弁がありました。
②根本市議は「スクールソーシャルワーカー」が学校でどんな役割があるのかをこう述べました。「教師が子どもの変化に気づき、生活の様子を子どもに訪ねると、経済的に困難をかかえた状態だということがわかります。そんな中で親は生活のこと、子育てのことで悩んでいるのではないかと心配をされているそうです。しかし、担任だけでは的確に対応できないというのが現状としてあります。また、外国人家庭の場合、言葉の問題で困っている上、子どもの問題があれば、日本語指導員の先生にそれ以上のことを求めることになります。そして、不登校などの子どもには、子どもの心の問題や、家庭、地域、学校等の子どもが置かれている環境の問題が複雑に絡み合っているものです。
これらの学校で起こっている問題に取り組むのが『スクールソーシャルワーカー』です。」
③そして、中学校区で活動するスクールソーシャルワーカーの配置を求めました。答弁では「スクールカウンセラーと学校コンサルタントで対応していく。外国人家庭には市民相談課の窓口の協力も得て行う。」ということでしたが、根本市議は「配置の検討すること」を求めました。
○就学援助制度の活用についての質問では①「入学時に説明している」という答弁があり、家庭訪問の時やPTA総会などで、全ての学年対象に毎年知らせることを求めました。さらに、就学援助の申請用紙を放課後児童クラブの部屋に置いて、指導員さんが制度について、保護者と相談ができるようにすることも提案しました。市からは「周知の拡大に向けてよりよい方法を検討していく」との答弁を引き出しました。
②また、民生委員の意見を申請の条件とする法的根拠がなくなったことを示し、民生委員の意見は申請の条件としない事を求めました。これに対して「適正な申請のための調査として貴重な資料の提供を求める」と答弁があり、根本市議はさらに申請の条件としないことを求めました。