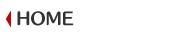市議団だより−市議団の主張
【10.04.07】二元代表制を考える…議会縮小は民意の排除
 名古屋市の河村市長が市議会に「市政改革」の一環として「議会改革」を提起しています。その最大の問題点は、市議会定数の半減とそれに伴う小選挙区制の導入です。政務調査費のムダ遣いなど議会に対する市民の不満をテコに、市長への権限を集中し「改革」を強行する専制体制を築こうとするものです。
名古屋市の河村市長が市議会に「市政改革」の一環として「議会改革」を提起しています。その最大の問題点は、市議会定数の半減とそれに伴う小選挙区制の導入です。政務調査費のムダ遣いなど議会に対する市民の不満をテコに、市長への権限を集中し「改革」を強行する専制体制を築こうとするものです。
だいたい、住民から直接選挙されている議会を、首長がつくりかえることが許されるのでしょうか。
憲法や地方自治法は、住民が首長と議員を直接選ぶ「二元代表制」をとっています。これには訳があります。
一つは、戦前の反省です。明治憲法のもとで、都道府県知事は天皇の任命で、市町村長は議会選出でしたが、事実上国の意思が反映していました。こうした中央集権体制が戦争翼賛の道具になったのです。
もう一つは、首長と議員がそれぞれに住民を代表し、互いにチェックしあって住民福祉を実現することをめざしたのです。「相互の抑制と均衡によっていずれかの独善と専行を防止する体制」(町村議会議長会編『議員必携』)とされます。
河村提案は、この「抑制と均衡」の考えに立った「二元代表制」を否定し、市長の専制政治を狙う民主主義破壊の暴挙といわなければなりません。河村市長自身、「二元代表制」を「立法ミス」と敵視しています。憲法に対する無知に基づく極めて乱暴な議論だといわなくてはなりません。
憲法が、首長について公選を定めるだけである一方、議会については議員の公選に加えて、明文で「議事機関」(93条1項)としているのも、そのことを示すものです。地方議会を単に「議決機関」とせず、「議事機関」とし、議決に至るまでの審議を重視していることに深い意味があります。
このような憲法の仕組みに照らすなら、首長が自分の意志を通すために議会の権限を弱めるなどという事は、憲法を正面から蹂躙するものだと言わなくてはなりません。