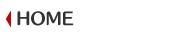市議団だより−市議団の主張
【10.11.29】2011年度予算に対する要望書を市長に提出…日本共産党市議団
29日、日本共産党豊田市議団は、鈴木公平市長に2011年度の予算要望書を提出し、懇談を行いました。
鈴木市長は、財政が厳しい中ではあるが、市民生活にかかわるサービス水準を落とさないように努力したい、と答えました。
日本共産党市議団からは、地域経済への対策、教育問題、平和市長会議などについて特に言及して懇談を行いました。市長からは予算編成の参考にし、また、文書でもきちんと回答するとの約束が交わされました。
◆◆◆◆◆予算要望書の全文は以下のおりです。
豊田市長 鈴木公平様
2011年度予算編成に対する要望書
2010年11月29日
日本共産党豊田市委員会
委員長 大村義則
副委員長 根本美春
日本共産党豊田市委員会は、2011年度予算編成にあたり、以下の項目についての実現を求めます。税金の無駄遣いや不要不急の事業を見直し、市民の生活・福祉・教育を重視し、地方自治法の基本原則にたって「住民の便宜及び福利増進」を図ることを求めます。
【総合企画部】
①人口の社会減が進んでいます。非正規労働者の解雇が原因であることを検証し、市外からくる労働者が定住できるように、正社員の採用を大企業に求めること。
②不況で外国人の雇用と定住が困難になっています。市内在住外国人への生活・就労など各種支援を強めること。県営保見団地の空家に入居できるように、対策会議を設けコミュニティの支援を行うこと。
③下山地区に予定されているトヨタテストコース・研究施設については、トヨタの開発・建築・施設計画を明らかにし、環境アセスは県企業庁が説明したように、それらの施設を含めて行うように求め、公聴会を開催すること。
●国・県・市が公として対応する周辺の基盤整備(道路・上下水道・該当地区のまちづくり)計画について開発者負担とし、その内容を財政支出の見込みも含めて明らかにすること。トヨタテストコース・研究施設開発に伴う雇用の増加、定住人口、地域振興などの経済効果を算出すること。公的な支援の額に見合うのか、費用対効果を算出し妥当性について明らかにすること。
●サシバ、ミゾゴイなど希少種の野鳥が生息しています。十分な環境調査を実施し、環境団体と話し合うこと。
④2010年5月に開催されたNPT再検討会議での合意文書は、「核兵器のない世界」達成のため、「必要な枠組みを確立する」「特別な取り組み」を確認し、とりわけ核兵器国に「いっそうの取り組み」を求めました。「核兵器のない世界」実現への強い決意を表明した潘基文国連事務総長は、みずから核兵器廃絶条約を提案しています。鈴木市長は「平和市長会議」に加盟をされました。これらの世界の情勢にそった平和行政を、豊田市としてすすめる事が求められています。
●近隣のみよし市も平和都市宣言を行いました。豊田市として、非核平和都市宣言を行い、それにもとづく平和行政をすすめること。
【経営政策本部】
①経済悪化にともなう市財政の影響を中長期的な観点で分析・検証し、市民生活に支障をきたすことのないように、適切な予算配分を行うこと。ハードより環境、福祉、教育の人的資本などのソフトを拡充すること。幹線道路・箱モノよりも生活道路、公園、住宅など生活関連施設を優先すること。
②「豊田市環境モデル都市」は、公共交通、自転車などを生かした都市づくり、都心での公園、緑の増加を目標とすること。一番排出の多い企業のCO2削減を優先すること。農林業の保全を環境政策の基本に位置付けること。都市環境政策を具体化し促進をはかるためにも、住民参加で、「地球温暖化対策条例」を策定し推進をはかること。
【総務部】
①野田市などを参考に、公の仕事を契約する企業には時給千円以上の確保や、所定労働時間・週40時間など、あるべき賃金や労働条件の確保を条例で義務付ける公契約条例を制定すること。
②市職員の配置については、仕事量や予算額の変化、社会情勢や市民ニーズの変化を適切に掌握し、必要な人員と専門的知識や技術を活かした職員配置を行うこと。公務職場における不安定な非正規雇用は縮小し、正規職員の拡充をはかること。任期付採用職員は育児休業代替の最小限数とすること。特別任用職員の時間給を引き上げること。経験年数による加算と一時金の支給をすること。
③職員の希望をよく聞き、市民に奉仕する公務員としての自覚と誇りを持って働けるようにすること。人事考課制度は相対的評価、単年度評価のため問題が多く見直すこと。特に、賃金格差を縮小すること。昇任・昇格における男女差別をなくし、女性職員の登用を積極的に行い、働きやすい環境を整えること。
【市民部】
①所得制限を付けた庶民減税を行うこと(大企業・お金持ち優遇になるような一律減税でなく)。低所得を理由とする住民税の減免制度を拡大すること。
②市民税の徴収については、失業者・営業不振、生活苦や病気などによる納税困難者には、個々の事情に即した納税方法を相談し、収納率強化のため悪質な滞納ではないのに資産の差押えなど行き過ぎた徴収は行わないこと。
③法人市民税について資本金の額に応じて税率を変える「不均一課税」を実施すること。その中で、大企業には制限税率を適用すること。
【社会部】
①武力攻撃事態法に基づく「豊田市国民保護計画」は、戦争に市民を総動員し協力させるものであり、凍結すること。
②犯罪が増えています。防犯パトロールやコミュニティ強化による犯罪の防止を引き続き強めること。地域から要望がある交番の新設、移転などについて、県に働きかけつつ、推進をはかること。防犯灯を増設し、明るい街にすること。消費電力のすくないLED電球に切り替えること。自治区負担を無くして、全額公費負担とすること。また、街路灯について設置基準を市民に周知しつつ増設すること。
③市の関わる行事に自衛隊の参加をさせないこと。
④市内で自衛隊が訓練を行う場合には、市に連絡をするように申し入れること。(※市街地での行軍訓練以外に、市内の山間地での訓練が行われているもようです。)
⑤合併5年目の節目を迎え、合併による影響を調査し、対策を講ずること。
⑥地域会議の自主性と住民参加を拡大すること。地域会議ごとの地域計画をつくること。地域会議の公募委員を増やし、議事録の早期公開、会議予定の事前公開、傍聴者の発言を認めること。支所職員の増加をし、地域自治区を充実すること。
【こども部】
①認可保育所を増やして、待機児を解消すること。政府が検討中の新たな保育制度「子ども・子育て新システム」は、保育に対する国や自治体の責任をなくし、保育への企業の参入・撤退自由化で子どもをもうけの対象にするものだと考えられ、大変危惧されます。政府に対して、慎重に検討するよう意見を述べること。
②学童保育について
●国の示したガイドラインにもとづき運営基準を策定すること。
●指導員は正規職員での雇用をめざし、少なくとも、専任指導員は正規職員とすること。プレハブではなく常設の専用施設を設置すること。
●小学校高学年も入れるように対象を拡大すること。障がい児、外国人児童の受け入れ体制を整備すること。
③放課後の子どもの安全な遊び場と生活の空間を確保するために、留守家庭児童を対象とした学童保育以外にも、放課後の子どもの居場所を小学校区ごとにつくること。
④こども園の保育士・教諭の長時間残業(持ち帰り残業も含めた)を改善すること。臨時・パートの拡大ではなく、正規の保育士・教諭の増員を行うこと。
⑤保育園給食を自園調理に戻すこと。
⑥特に、学校、子ども園など、子どもと関係が多い職場に子ども条例の周知を図ること。とよた子ども権利相談室の周知につとめて、相談活動を強化すること。
⑦妊産婦健診は初回から公費助成をすること。
【環境部】
①ゼロエミッションの方針に基づき、全市的な産業廃棄物の削減目標を明確にした条例に改正すること。
②産業廃棄物と残土の適正処理を徹底するとともに、市独自の水源保護条例を制定して、産業廃棄物処分場を規制すること。
③環境アセスメント独自条例を制定し、住民参加と情報公開、代替案の検討を義務づけ、事後評価を実施すること。さらに欧米で導入されている「政策の計画段階からの環境アセスメント(戦略的アセスメント)」の実施を行うこと。
④太陽光・熱、小水力、バイオマスなど自然エネルギーの設備設置への補助を手厚くし、発電量に応じた助成の創設を行うこと。小規模水力発電を中山間地に設けること。当面、モデル事例をつくり研究を深めること。
【福祉保健部】
①介護保険の保険料、利用料の引き下げのため、一般会計からの繰り入れを行うこと
●保険料の減免制度が、預貯金などの厳しい制限のため、ごく僅かしか受けられていません。対象条件を緩和すること。
●利用料の減免制度について、軽減額をさらに拡大すること。
●すべての要介護認定者を障がい者控除の対象とし、「障がい者控除対象者認定書」を送付すること。
●介護労働者を確保するために、賃金や家賃助成などの支援を行うこと。
②特別養護老人ホームや小規模多機能施設など施設・在宅サービスの基盤整備の推進をはかること。基盤設備が円滑に進み、低所得者・医療依存度の高い利用者の入所が確保できるよう助成制度を設けること。申し込みによる優先順位の基準を明示し、公正に行われるように市として指導すること。
③現行の障害者自立支援法の継続にあたっては、以下の事項を早急に具体化するよう国に申し入れること。
●自立支援医療を利用する住民税非課税世帯の利用料を無料にしてください。
●利用者負担の際の収入認定は、障がい者(児)本人(個人単位)としてください。
●移動支援等の地域生活支援事業に対する予算を増額してください。
●施設利用者に対する食費・水光熱費の自己負担を撤廃してください。
●実態に合わない障害者程度区分認定の見直しとともに、それを基準としたサービス利用の制限を撤廃してください。
④国に対して国保会計への負担割合を増やすよう求めるとともに一般会計からの繰り入れをさらに増やし、基金を取り崩すなど必要な施策をこうじて国保税を、少なくとも1世帯1万円引き下げること。
●18歳未満の子どもについては、均等割の対象としないこと。
●「低所得」を要件とする国保税の減免制度を拡充すること。
●一部負担金の減免制度について、生活保護基準の1.4倍以下の世帯に対しても実施すること。
⑤後期高齢者医療制度を早期に廃止するように、国に意見を表明すること。対象者に対し、保険料の減免制度を設けるとともに、保険料滞納者に対する短期保険証の発行をしないこと。
⑥75歳以上の医療費無料の制度を創設すること。
⑦ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸ガンワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチンの任意予防接種の費用について、助成する制度をつくること。上記ワクチンを定期接種とするよう国に働きかけること。
⑧交通の便のよい市中心部に医療施設体制を整えるため、中心市街地に地域医療センターを移転新築すること。医療の空白地域とも言える南部に医療センターのような公的責任を持つ診療機関を設置すること。小児救急に対応できる公立こども病院の新設を検討すること。改
⑨被雇用者の自殺者数が多いとされる現状をふまえ、引き続き、原因究明や相談体制の強化など自殺者数を減らす手立てを講ずること。自殺との関係が強いうつ病患者の推移を掌握し、対策を講ずること。愛知県のように総合的な自殺対策を策定し、庁内での横断的な対策会議を行うこと。
⑩正規職員の生活保護のケースワーカーを増やし、保護の対応を速やかに行う体制を整えること。
⑪介護要件などの制限を設けずに、全ての高齢者世帯、昼間独居の高齢者を対象に緊急通報システムを設置すること。
【産業部】
①トヨタ自動車をはじめとして、市内の大企業は期間工や派遣労働者などの「非正規従業員」を大量に雇い止めしました。「最高2年11カ月働ける」といって募集しながら契約更新をせずに次々と雇い止めし、社会的批判をあびました。その結果、豊田市の人口も09年は社会転出が超過しました。さらに、トヨタ自動車高岡工場では、2010年12月から、1900人もの労働者を市外も含めた他工場へ転籍させる計画がすすんでいます。また、高岡工場で生産している主力車種であるカローラの輸出分を2013年以降、すべて海外の工場に移すという報道もされています。1900人もの労働者の転籍で移動させるという事は、普通の自治体であれば、大問題となるところでしょう。1つの大きな工場の閉鎖とか、休止に値する規模です。そこに働く労働者は市民であり、下請け企業にも、当然、大きな影響があると思われます。
●このような企業活動の大幅な変更については、まず、行政に対して報告させる事、市民生活や地域経済に大きな影響を及ぼさない計画とすること、などを市長として大企業に要請すること。
●市長を先頭に大企業にたいして解雇・雇い止めをやめ、正規雇用を増やすよう働きかけること。
●緊急経済対策で市独自の雇用創出事業を、引き続き進めること。
②経済対策として、蒲郡市のように住宅リフォーム助成制度をおこなうこと。
③企業誘致推進条例で助成する企業には、正規社員の採用を指導すること。
④「ものづくり」が製造業の自動車に特化しすぎ、「一極構造の脆弱性が発現」しています。多様な工業の振興と農林業、商業も含めたバランスのとれた産業構造とし、大企業の「成長」だけでなく維持可能な社会へと転換していくこと。新産業振興策は愛知県のように、労働を考慮した政策とすること。
⑤国の中小企業憲章を踏まえ、中小企業振興条例を制定し、中小企業支援センターを設置すること。それにより、創業支援、技術向上、製品試験、研修・交流などの機能が発揮できるよう、産業振興のセンターとして位置づけ、専門家など人的体制を充実させること。中小企業の実態を調査し、大企業に下請け単価の改善を働きかけること。
⑥中小零細業者への支援策として「小規模工事の契約希望者登録制度」を創設すること。
⑦信用保証料100%補助を継続し、中小企業の資金繰り対策支援を強めること。
⑧店舗の閉鎖が増えています。そのために発生する「買い物難民」をなくすために、行政支援すること。商店街の活性化支援を強めること。
⑨豊田市の食糧自給率は国の40%を大きく下回っています。その原因を明確にすること。国は50%の拡大目標を設定しています。食料自給率の指標は農業政策の基本指標であり、市としての数値目標を明確にすること。
※豊田市の「行政経営」では、数値で目標を持つことを基本的な考えにしているはずです。
⑩TPPに反対し、ミニマムアクセス米の輸入をやめるよう国に求めること。
⑪有機野菜・低農薬農業を奨励し、直売所を増やし、安全・安心な「豊田野菜」の供給で地産地消の拡大を図ること。
⑫合併した中山間地域の仕事おこしのために、間伐や道路脇の林の伐採を公共事業として発注するしくみをつくること。
【都市整備部】
①市営住宅の入居待機者をゼロにできるように、建設計画をつくり年次計画を示すこと。建設計画のない場合は民間賃貸住宅の借り上げや家賃補助などで、住宅困窮者の救済を進めること。(豊田市住宅マスタープランにもとづき、何年度で待機者がゼロになるか、示してください)。県営保見住宅の空家約300戸を募集するよう要請し、コミュニティなどの問題解決に協力すること。派遣切りなど職と住居を失った人の緊急住宅を確保すること。雇用促進の空家が活用できるようにハローワークと協力して進めること。高齢者、障害者、母子家庭、外国人が、民間住宅に入居できるように、「あんしん賃貸事業」の前年度の入居者を把握し、問題点を見直し県と協力して改善すること。
②全市的なコミュニティバス網の整備をすすめ、公共交通の推進をはかること。
●コミュニティバス利用促進のためにも、高齢者・障がい者への無料パス制度を創設すること。バスどおしの乗り継ぎや、鉄道とバスの乗り継ぎ等、公共交通機関どおしの乗り継ぎによる割引制度をつくること。
●バスの本数を増やし、鉄道の時刻にあわせるなどバスのネットワークの連携をよくして、利用しやすい公共交通を構築すること。
③民間建築のアスベストはアンケート調査でなく、市で実態調査を行うこと。国の補助制度の実績を明らかにし、助成制度を活用すること。
④駅のバリアフリー化を促進するとともに、汚い駅トイレの改善を事業者に申し入れること。危険な踏み切り箇所の調査を行い、改善を事業者とともにすすめること。
⑤駅前通り北地区再開発計画への税金投入のあり方について、過去の教訓をきちんと検証すること。それをふまえて、市民の理解が得られる内容を前提に行う事。
【建設部】
①市街地に身近な公園、雨でも子ども達が遊べる施設を増やすこと。特に市街化区域では小学校単位で整備目標と計画を作ること。公園の草刈、枝の剪定を定期的に実施し、遊具を増やし、安全確保を重視した点検・管理を行うこと。また、必要な照明・手洗所・トイレを増やすこと。
②既存市街地の生活道路の整備を進めること。市道の歩道整備状況と整備目標、年次目標を示すこと。
③歩道の設置、自転車道の整備を(市中心部だけでなく)推進すること。また、歩道に車が乗り入れないように、セミフラットやボラードの設置などでバリアフリーを進めること。車のスピードを落とす必要のある個所では、車道にハンプを設けること。車いすやシニアカーで通行する際、デコボコや傾斜のある歩道で危険を感じるという声が少なからず寄せられています。安全に通行できるように整備すること。
【消防本部】
①予想される東海・東南海地震などの災害に備え、消防力の抜本的強化を図ること。女性消防職員を増やし、各署の仮眠室の改善を図ること。
②救急救命士を一層充実させて救命率の向上を図ること。
③消防団の器具庫・詰所などの拡充をすすめること。消防団員の出動手当ての引き上げなど待遇改善にいっそう努めること。
④火災予防条例の改正をふまえ、個室ビデオ店、ネットカフェ等への指導を強めること。また、ビル管理など定期点検の徹底と火災予防にむけた指導を引き続き強めること。
【上下水道局】
①上下水道事業は公営を堅持し、安くて安全な水を供給すること。
②低所得者に対する利用料減免制度を創設すること。料金滞納者については、親切・ていねいな対応を行い、機械的停水措置はとらないこと。
③マンション等における水質検査及び衛生確保など、貯水槽水道の管理について徹底をはかること。
④下水道整備を進めるにあたって、地域の道路整備や地区の計画と連携して効率的にすすめること。
【教育委員会】
①小中学校のすべての学年で少人数学級を実施すること。その中で正規教員を増やし、教員の多忙化を解消し、子どもの教育に専念できる条件をつくること。
②教職員の労働時間把握を行い、時間外労働の縮減に具体的に取り組むこと。教職員の事務量を軽減すること。
③臨時教員や非常勤講師の賃金と労働条件を改善しつつ、正規教員への採用をすすめること。
④就学援助制度を拡充し、申請の受付は学校だけでなく市の窓口でも受け付けるように改善すること。また、申請手続きに必要としている民生委員の証明はなくすこと。
⑤いじめや不登校対策は、スクールカウンセラーの時間数を増やし、体制を整えるとともに、不登校・ひきこもりなど、子どもの問題に取り組んでいる民間団体への援助を行うこと。
⑥軽度発達障害の子どもの増加や学級崩壊の状況を正確に把握し、学校への支援体制を強化すること。学級運営に困難をかかえるクラスへの学級運営補助指導員を増員すること。
⑦豊田市から知的障がい児が大勢通っている三好養護学校は、全国ワースト10に入る「マンモス校」になっています。知的障害児のための養護学校の新設に向けて、市議会での答弁を踏まえて、早期に実現すること。一人ひとりの子どもの発達を保障する障害児教育を充実するため専任の教員を増員し、通級指導教室を増設すること。
⑧子どもの貧困が深刻になっています。子どもの環境の要因を把握し、学校の枠を超えて、市役所や児童相談所などの機関との連携をより一層強くし、福祉的な援助を行う「スクールソーシャルワーカー」を学校に配置すること。
⑨小・中学校に通う児童・生徒の遠距離通学の支援策を拡充すること。
⑩大規模校の解消をすすめること。
⑪「エコスクール」の検証を行いつつ、普通教室の暑さ対策をすすめ、必要に応じて扇風機、クーラーの設置を行うこと。
⑫一般家庭の洋式トイレの普及状況をふまえて、学校トイレの洋式化をすすめること。
⑬教育費無償の原則にたち、学校給食は無料とすること。安全で豊かな学校給食のために、地産地消をいっそうすすめ、自校方式を復活させること。
⑭教材費の保護者負担をなくすこと。すくなくとも、「算数セット」「鍵盤ハーモニカ」「リコーダー」などは、学校備品して購入して、使用したほうが合理的であり、資源のムダにもならないと考えます。
⑮専任の図書館司書の全校配置、図書整備費の増額で学校図書館の充実をはかること。
⑯舞台やコンサートなど市民が使いやすい中規模の文化ホールの建設を進めること。公共の貸館としての会議室が不足しているので、増設すること。
⑰民間委託したスタジアムの運営費には、これ以上、公費をつぎ込むことはやめること。独立採算で運営できる計画を立てること。
⑱豊田の戦争遺跡を調査し、保存すること。戦争時の記録、資料を郷土資料館などに常設し、平和担当職員を置くこと。