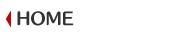市議団だより−議会&市政の報告
【14.08.28】水道料金「1トン1円上乗せ」基金 新方針を市がようやく提示
日本共産党市議団の徹底追及で市が動く
「水道水源保全基金」が問題になっています。
豊田市当局は、8月4日付で市議会に対して「水道水源保全事業のリニューアル」と題した資料を提出しました。
◆水道水源保全基金、貯金ばかりで約7億円
豊田市は、「安全でおいしい水道水」の供給のために、「水源涵養事業」や「水質保全の環境整備」などを進めるとして、水道料金に、「使用量1トンあたり1円」を上乗せして基金に積み立てて目的の事業を行うとしてきました。一年間に市民が水道料金の「上乗せ分」として支払っている金額は4600万円余にもなります。
しかし、実際に「水源涵養事業」や「水質保全の環境整備」事業に使うのは年間収入のうち、800万円余。ほとんどの残金は基金に積み立て続けてきました。今や、その積立残高は、6億8千万円にも達しています。
日本共産党豊田市議団は、予算審議、決算審議のたびに、「『貯金』するだけで、水道水源保全事業という本来の目的が果たされていない。間伐事業の推進など、本来の目的にそって使い方を改善すべきだ。それができないなら、水道料金を値下げせよ」と迫ってきました。
◆市町村合併により、使い方に矛盾が
この事業の経過をみてみると、市町村合併と大きくかかわっています。
実は、水道水源保全基金は、平成12年度から16年度までは、水源地域の山林の間伐事業に大きく使われていました。矢作川上流域(旧藤岡・小原・足助・下山・旭及び稲武町)と、水道水源保全基金を活用した間伐事業の基本協定を締結し、矢作川上流の森林保全事業を行っていたからです。
しかし、平成17年の市町村合併により間伐事業の区域がすべて豊田市となり、その使い方が迷走します。合併豊田市として、市の一般財源を使って水源である旧町村地域の間伐ができるようになりました。実際、合併豊田市では、森林課を設置して、一般財源(通常の税金収入による)で間伐事業を積極的に推進するようになりました。使い道を失った「1トン1円」は、「貯金」するしかない状況に陥ったわけです。
市町村合併により、「1トン1円」の上乗せの根拠が揺らぐことになりました。合併前は、当然ながら、上流域の旧6町村住民のみなさんの水道料金には、「1トン1円」は、上乗せされていません。下流域の住民が「安全でおいしい水道水」の恩恵の見返りとして負担しようという趣旨でしたから。
ところが、合併で、上流域の住民のみなさんも、みんな「1トン1円」を負担する事になってしまいました。そうだとすると、そもそも、この事業は、水道料金の上乗せで対応するべきものではなく、税金で対応すべきものではないかという事になるわけです。
◆1トン1円」上乗せの見直し必要
今回、市当局が発表した「水道水源保全事業のリニューアル」の方針では、新たに①水道水源間伐事業 ②水道水源林確保事業 ③水道水源モニタリング事業をすすめるとしています。元々、この水道水源保全基金の制度をつくった時の出発点に立ち戻った事業をすすめるという事です。
山林の間伐を中心に、水源の森を守り「安全でおいしい水道水」を確保するという施策には大賛成です。一般財源で支出している間伐事業を基金残高6億8千万円にもおよぶ財源で実施すれば、その分を他で使う事のできる財源にも充てられます。
その一方で、前項で指摘した、そもそも水道料金の上乗せで対応すべきなのかという問題は残ったままです。
もともと、この問題は、市町村合併時に解決しておくべき問題でした。政策判断をせずに、10年間ずるずると引き伸ばし、市民から集めた7億円近くの財源を眠らせておくだけにしてしまった。市長をはじめ、関係部局の責任が問われます。
日本共産党豊田市議団は、当面、「水道水源保税事業のリニューアル」で示された、間伐をはじめとした事業に賛成しつつも、水道料金に「1トン1円」を上乗せする事を見直す等、より根本的な対応をもとめていきます。