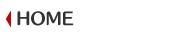市議団だより−豊田のまちから
【09.02.10】トヨタ、労働者冷遇 株主配当に偏重
 トヨタは二〇〇〇年代に入って、世界一の自動車メーカーに成長しました。そのなかで、トヨタの経営体質にも大きな変化が生まれています。
トヨタは二〇〇〇年代に入って、世界一の自動車メーカーに成長しました。そのなかで、トヨタの経営体質にも大きな変化が生まれています。
かつてトヨタの奥田碩会長(当時)は、日経連会長時代に、「経営者たるもの、首を切るなら、腹を切れ」といったものですが、そのトヨタがいまでは、「派遣切り」「非正規切り」の引き金を引いています。それにはわけがあります。トヨタは金融・住宅バブルにおどるアメリカ市場に進出し、収益を拡大するために、「アメリカ型経営」をとるようになったからです。
「アメリカ型経営」と「日本型経営」には大きな違いがありますが、その一つは内部留保です。アメリカの企業は、日本のように膨大な内部留保を蓄積することはありません。利益は、株主と経営者に厚く配当します。
トヨタは「日本型経営」にもとづく膨大な内部留保をため込むことと同時に「アメリカ型経営」にもとづいて株主重視の配当をするという経営に変化します。内部留保はこれまでどおり増やす、そのうえ株主配当もアメリカ企業並みに増やすというように変わってきたのです。
配当金が急激に増えています。一株当たり配当金は、〇三年度の四十五円だったのが、〇七年度には百四十円に跳ね上がりました。配当金総額は。同じ時期に千五百十二億円から四千四百三十二億円へと三倍にもなっています。役員報酬も重視されました。〇三年度の一人当たり役員報酬は七千万円でしたが、〇七年度は一億二千二百万円へと五千万円以上も増えています。
株主重視、役員重視の経営のもとで、トヨタの正規労働者の平均賃金は、トヨタが大もうけをしていた〇三年度から〇六年度には低下傾向にあり、〇三年度の八百二十二万円から〇六年度の八百万へと二十二万円減少。〇七年度には、若干上がりますが、それでも八百二十九万円です。
正規、非正規を問わず、労働者すべてを踏みつけにして、株主や役員重視の経営をするようになったのです。この経営体質を転換させ、労働者や下請け・関連企業、地域経済などへの企業の社会的責任をはたさせることが必要です。なかでも、「非正規切り」をやめさせることは、急務です。トヨタはことし三月末までに、契約満了ということで一万人前後の「非正規切り」をおこなおうとしています。しかし、トヨタは、雇用を確保する体力を十分持っています。
非正規労働者の賃金を年間三百万円として計算すると、仮に一万人の非正規労働者の雇用を守ろうとすれば、必要なお金は三百億円にしかすぎません。株主配当を減らしても、内部留保を少し削っても、すぐにもできることです。株主配当金の総額は、〇七年度四千四百三十二億円です。6・7%減らせばいいのです。十三・九兆円の膨大な内部留保は、わずか0・21%取り崩せば、「非正規切り」をやめさせることができます。
トヨタの「赤字」宣伝は、こうした強靭(きょうじん)なトヨタの企業体力を覆い隠して、「非正規切り」をはじめとした労働者いじめを合理化するものとなっています。(日刊しんぶん『赤旗』より)