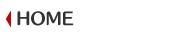市議団だより−市議団の主張
【09.04.18】内部留保を雇用維持に使え
「株主には配当で大盤振る舞い、労働者は切り捨て」は、認められない
 大企業の「派遣切り」が広がる中で、「内部留保」の活用を求める声が高まっています。
大企業の「派遣切り」が広がる中で、「内部留保」の活用を求める声が高まっています。
「内部留保」とは、そもそも何なのか? それを使って雇用問題を解決することができるのでしょうか?
「内部留保」とは、企業がため込んだ利益のことですが、大きくいって三つの部分からなっています。
●利益剰余金…毎年の利益から株主に配当した残りを積み立てたもので内部留保の中で一番多くの金額を占めています。
●資本剰余金…資本取引で発生する利益です。たとえば、株式を時価発行した際の収入のうち、半分は「資本金」となりますが、残りが「資本剰余金」として積み立てられます。
●引当金…企業会計上は、「利益」に計上されず、「負債」として計上されますが、実際の支払いは将来のことなので、当面は積立金のようになります。一種の「隠し利益」です。
◆「株主のものだから使えない」は道理がない
「利益剰余金は、株主に配当すべき利益を保留したものだから、株主のもの。経営者の判断で雇用維持に使うことはできない」との議論があります。
たしかに、株式会社は形の上では出資者である株主のものですから、利益剰余金の使途に限らず、会社の決算は株主総会の承認を受ける必要があります。だからと言って、株主の利益だけを優先し、株主のためなら何をしてもかまわないということにはなりません。
いま、大企業が行っている「派遣切り」は、三年の期限を超えて使用してきた労働者を解雇するなど、現行の労働者派遣法などに照らしても違法の疑いが濃いものです。いくら「株主のため」と言っても、こんな無法が許されるはずがありません。
内部留保を使うのに、事前に株主総会の承認が必要なわけでもありません。「6月の株主総会が終わるまで3月の給与が払えない」などという経営者は、どこの会社を探してもいないでしょう。雇用を維持した結果、当年度の決算が赤字になれば、その段階で内部留保を取り崩して損失処理する事を株主総会に提案し、事後的に承認を受ければいいのです。
◆「設備投資や原材料に使われている」は根拠なし
「内部留保は現金で残っているわけでなく、設備投資や原材料の購入に使われてしまっている」という言い訳もされています。しかし、これも現実とは違います。
ここ10年あまり、大企業の内部留保は大きく増えましたが、土地や工場・機械などの「有形固定資産」や製品在庫・原材料などの「たな卸資産」はほとんど増えていません。増加した内部留保が設備投資なと゜に使われてしまっているという首長は、まったく根拠がないのです。
◆「手元資金がないと困る」は事実と違う
「金融危機で、大企業も資金繰りが大変になる。給与を余分に払うと手元資金が減って困る」という議論もあります。たしかに「手元資金」は減ってきています。しかし、これは、景気が悪くなって資金繰りが苦しくなったために減ったわけではありません。内部留保がどんどん増えていたにもかかわらず、大企業自身が「現金で手元に置いていても非効率だから」といって、手元資金をギリギリに抑え、内部留保の多くを株式や公社債などの証券投資に振り向けてきたからです。トヨタ自動車の場合、手元にある現金・預金は1.7兆円ですが、そのほかに国債だけでも1.8兆円保有しており、他に株式や社債などの形で多数を保有しています。「手元資金がないと困る」というのなら、それらの株式や公社債の一部を換金すればいいだけのことです。
◆本音は「株主配当を減らしたくない」!
なぜ、大企業は、根拠のない理屈をこねてまで、内部留保を雇用維持に使うことに抵抗するのでしょうか。それは、結局、「利益が減っても株主への配当は維持したい。そのための原資として内部留保は取り崩したくない」からです。
配当だけではありません。この間、大企業は「自社株買い」といって、利益や内部留保の一部を使って自社の株式を市場から購入してきました。市場に出回っている株式数が減れば、株価が上昇し、株主にとって利益となります。一種の「隠れ配当」です。配当と自社株買いをあわせた「株主還元」が当期純利益を上回るような企業さえ生まれています(07年のキャノンの例)。この配当を少し減らせば、雇用維持の財源を確保できる企業がたくさんあります。
「内部留保を活用して雇用を守れ」の声は、今や国民の声。その実現のために力を合わせましょう。