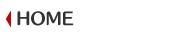市議団だより−市議団の主張
【09.04.28】中小零細事業者の仕事増やす緊急対策を
小規模公共工事を受注しやすくして!
 不況が深刻化する中、自治体が発注する小規模な工事・修繕などの受注機会の拡大を求める声が広がっています。
不況が深刻化する中、自治体が発注する小規模な工事・修繕などの受注機会の拡大を求める声が広がっています。
◆小規模工事の受注、「随意契約」なのに入札資格がいる
豊田市では、130万円以下の小規模の工事は「入札」ではなく、「随意契約」で受注できると定めています。
ところが市内にある中小零細の建設業者の多くが、この130万円以下の小規模な工事・修繕などの仕事が直接受注できていません。入札資格がないからです。130万円以下は入札でなく、随意契約でできるとしているにもかかわらず、それを受注するには入札資格を持っていることを前提条件としているからです。
◆建設業許可」より高いハードルの入札資格がカベ
公共の仕事は質を確保することが必要だから、入札資格のある技術水準が求められるという意見もあります。しかし、それは事実に反しています。
技術水準や経営水準の審査を受けてパスした「建設業許可」という資格があります。実は、市内で建設業を営む事業者の多くは、この建設業許可を持っているのです。この建設業許可は、一般に500万円以上の建設を請け負う場合必要とされる水準とされ、質も確保できているのです。ところが、市の入札資格は建設業許可のハードルよりも高い「経営事項審査」というハードルを設けて、それをパスしなければ随意契約でも受注できないとしているのです。
民間の仕事なら500万円以上の仕事ができる確かな腕と質を持っていながら、市の仕事になると随意契約でできるはずの130万円以下の仕事でも受注できない。結局、そういう小規模な工事でも入札資格を持っている元請の事業者が随意契約で受注し、実際の仕事の多くは中小零細の下請けがやっている。現実は質の確保された仕事を下請けがやっているというのが多くの現実の姿です。
◆全国で広がる「小規模工事登録制度」。ぜひ豊田市でも
他の自治体でも同じような状況がありました。そこで入札資格を要件としないで、希望する業者が簡単な手続であらかじめ登録しておけば小規模な公共工事を受注することのできる制度…「小規模工事の契約希望者登録制度」を作る動きが全国で広がっています。
全国商工団体連合会の調査によると、この「小規模工事登録制度」の実施が、46都道府県411自治体に広がっていることが明らかとなりました(4月27日発表)。市町村合併によって自治体数が減少するなかで、前回の調査(07年10月)よりも56自治体増え、全市町村(1777)の23%が実施しています。
今回の調査結果を見ると、市町村が「小規模工事登録制度」を緊急経済対策として位置づけ、予算枠や工事の上限額を引き上げている点が注目されます。
秋田県湯沢市は先ごろ、小規模事業者登録制度を緊急経済対策として位置づけ、前倒しで発注することを決め、1000万円の補正予算を計上したとしています。
広島市では発注する50万円以下の小規模修繕の予算4億円のうち3億円は学校関係が占めていることから、施設課長が「1件30万円までは学校長に権限があり、年間150万円の予算を持っている。制度の趣旨を徹底して発注を増やしたい」と答えたといいます。
豊田市では、この「小規模工事登録制度」そのものがありません。緊急経済対策として、まず、制度そのものの創設が求められます。