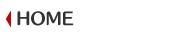市議団だより−議会&市政の報告
【10.06.18】障がいのある子ども達の教育条件改善のために…6月議会大村市議の一般質問
 日本共産党の大村よしのり市議は、16日、市議会の一般質問に立ち、「障がいのある子ども達の教育条件改善のために」とする質問と論戦を行いました。主な内容をお伝えします。
日本共産党の大村よしのり市議は、16日、市議会の一般質問に立ち、「障がいのある子ども達の教育条件改善のために」とする質問と論戦を行いました。主な内容をお伝えします。
◆障がいのある子どもたちが増えている◆
市内の小中学校で学ぶ、障がいのある子どもたちの数は、1484人(平成17年度)から1781人(平成21年度)に増加している事が、質問への答弁によって分かりました。
◆軽度発達障害の子どもが増えているが、「学級運営補助指導員」の配置が追いついていない◆
通常の学級に在籍している軽度発達障害のある児童生徒の数は、小学校502人、中学校121人、合計623人(平成21年度)にのぼるが、「学級運営補助指導員」の配置は109人であり、実態に追いついていない事が、答弁で確認できました。
大村市議は、「『学級運営補助指導員』の配置を提案し、推進してきた者として、増員を積極的に行うよう」提起しました。
○学級運営補助指導員って何?
平成12年度、県の緊急雇用対策として非常勤講師を採用して、学級困難な所に複数配置しました。初めは市内12校に配置されました。しかし、緊急雇用対策が目的なので期限付でした。大村市議が、緊急雇用対策の枠がなくなっても市が独自に実施できるように議会で提起し、市は、独自の採用で非常勤講師の配置を増やしていきました。その中で、現在の、学級運営補助指導員という制度に発展しました。他市にはあまりない、優れた制度です。
◆通級指導教室の配置が遅れている◆
市内で通級指導教室が置かれているのは6小学校、1中学校。通級指導教室を担当する教員も7人しかいません。一方で、発達障害のある子どもが在籍しているのは55小学校、23中学校にのぼることが、答弁で確認できました。
大村市議は、「学校現場や保護者にも、まだ通級指導教室の理解が広がっていない。通級指導教室の増設が必要だ」と提起しました。
○通級指導教室って何?
通常の学級で授業を受けながら、障害の状態などに応じて特別な指導を受けるために通う教室。従来の言語障害や難聴などに加えて、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症などの子どもを指導する場としても位置づけられています。
◆特別支援学級で、子どもの成長をていねいに支える教員の体制が必要◆
通常の学校で障がいのある子どもが学ぶクラスが特別支援学級です。
特別支援学級では、児童生徒への指導は全て個別対応となります。クラス編成は低学年から高学年まで一緒ですので、教える内容も子どもごとに違います。現場の教員からは「一人で受け持てるのは5人程度まで」との声を多く聞きます。
現状は、3人以下が80学級、5〜6人が54学級、7〜8人が8学級ある事が、答弁で確認されました。
大村市議は、「8人も受け持っている先生がいる。市採用の教員を配置して、子どもの成長をていねいに支える教育ができるように」提起しました。
◆三好養護学校のマンモス校化は放置できない現状◆
三好養護学校(全校419人)に通う豊田の子どもは213人。全校の半分以上が豊田の子どもたちです。
大村市議は、市立での設置も含めて、早急に教育条件の改善が必要だと提起しました。
市当局も、「改善が必要という思いは全く同感」として、県に強く働きかけ、具体的な方策を含めて県と話し合いたいと答えました。
○大村市議が視察に基づき議会で訴えた三好養護学校の現状
「丘陵地に校舎の増築を重ねたために、養護学校としてはあるべきでない階段がたくさんあり、バリアフリーとは正反対の施設となっています。
教室が足りないので、特別教室は言うまでもなく、教材室などの倉庫としての部屋も、そのほとんどが教室として使われています。つまり、倉庫を改造して教室として使っているわけであります。当然、倉庫に入るべき機材などは、棚と一緒に廊下出ています。
200人を越える教職員の職員室はまるで体育館のような大きな部屋で、朝礼や職員会議で声が聞こえないので、マイクを使って話します」