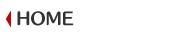市議団だより−議会&市政の報告
【10.07.28】子どもの笑顔を取り戻すために、子どもからのSOSに対応…とよた子どもの権利相談室が報告書まとめる
◆「子ども条例」と「とよた子どもの権利相談室」
市では、子どもの権利を保障し、子どもが幸せに暮らすことのできるまちを実現するために平成19年に「豊田市子ども条例」を制定しました。そして、条例制定の重要なテーマである「子どもの権利の侵害に対する救済と回復」を支援するために「豊田市子どもの権利擁護委員制度」をつくりました。
日本共産党市議団は、子どもを1人の人間、権利の主体として尊重し、権利侵害から守る条例の趣旨を重視し、制定に尽力してきました。
◆独自性、第3者性をもつ子どもの権利擁護委員
「とよた子どもの権利相談室」は子どもが感じている身近な悩みやSOSへの対応として独自性、第3者性の機能を持つ「子どもの権利擁護委員」が子どもの最善の利益を考えて、子どもと一緒になって解決を図る専門機関です。
開所して1年6ヶ月を経ました。年度ごとに活動報告書を作成し、市民に活動を知らせています。
◆子どもの権利擁護委員と子どもの権利相談員
相談室には「子どもの権利擁護委員」と「子どもの権利相談員」が配置され、相談にのっています。
子どもの権利擁護委員の仕事は「子ども条例」で定められています。
①子どもの権利の侵害について、子どもまたはその関係者から相談をうけ、その救済と権利の回復のために、助言や支援などをすること。
②権利の侵害をうけている子どもについて、本人または関係者から救済の申し立てを受けて、事実の調査や関係者間の調整をすること。
③子どもが権利の侵害を受けていると認めるとき、自らの判断で調査すること
④調査や調整の結果、必要と認めるときに、子どもの権利を侵害したものに対して、是正措置を講ずるよう勧告したり、制度などの改善を要請したりすること、などです。
◆相談の事例から
調査・調整活動について、報告書に記載されている事例を紹介します。(報告書への案件の掲載に当たっては申立人の了解を得ています。)
例1:相談者は市内の高校生で、「教員による生徒への不適切な発言・行為」に対しての相談。擁護委員が学校に対して、事実の確認をおこなった。この結果、生徒への指導について「配慮を心がけていただける」ものと判断し終了。
例2:教員による生徒への暴言・暴力等についての相談があり、擁護委員が事実の確認を行った。学校から「教員と子どもたちの間で感情のすれ違いがみられるので、指導を行っている。」との回答を得て、調査終了。
調査活動を行ったうちの一部ではありますが、擁護委員の直接の行動によって、改善が図られる結果となりました。
◆相談回数は532回
相談室では、8人の相談員が交代で相談にあたっています。相談室が受けた新規の相談は83件で、相談は1回で終わるものもありますが、その後、何回か続く場合もあります。相談に基づいて行った調査や調整活動を含めると相談回数はのべ532回でした。
子どもによる相談はすべて電話で29件。相談員が子どもたちからの相談を受けた感想には、子どもに寄り添って一緒に解決の方法を見出していく姿勢や、「相談してもいいんだ」と子どもたちが思うきっかけを作ることなどがつづられています。(21年度報告書より)