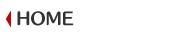市議団だより−議会&市政の報告
【16.09.22】中央図書館の指定管理問題
「異例」な進め方、疑念深まる
豊田市中央図書館の管理運営を、市直営から指定管理に変える条例案が9月議会で上程されました。
指定管理をめぐっては、導入凍結を求めて市民の署名運動にまで発展。6月議会の一般質問で、根本みはる市議は、議会の条例改正の前に、事業者の公募をおこなうことは、議会の軽視であり、計画は白紙撤回し、市民の声を聴くべきだと求めていました。
市は指定管理への変更で「司書の専門性確保、開館時間の延長でサービス向上ができる」としています。しかし、市直営では、なぜ司書の増員・司書の専門性の確保ができないのでしょうか。司書は経験と知識の蓄積が必要な専門の職務です。直営だからこそ、「確保」と「専門性」を高め、継続できるのではないでしょうか。
また、開館時間の延長の検討においては、「特任職員などの勤務時間が増え、費用が3千万円かかることから、費用対効果の点からも妥当でない」と説明。市は、最初から指定管理ありきの姿勢でした。
◆「先に公募」は脱法的手法ではないか
9月議会では、大村よしのり市議が条例議案の質疑をおこない、問題とすべき点が明らかになりました。
そもそも、今回9月議会での条例改定の前の、7月の段階で事業者の公募をおこなっていた事は、法令に違反していないのでしょうか。豊田市で、指定管理の在り方として、「条例改正より先に公募をしたことは1度もない」ことが答弁で明らかとなりました。大村市議の質疑に対し「事業者の募集・選定については、地方自治法では定められていない。自治体の裁量でできる」と強弁。まるで法の抜け道を行くやり方です。
◆業務のあり方は偽装請負にならないか
指定管理に変わった場合、市の(仮)図書館管理課を中央図書館の7階に設置し、「事業者にすべてを丸投げにしない」との説明が行われています。
しかし、方針決定をおこない、基幹部分を担う市の(仮)図書館管理課が事業者と直接係わる業務上の関係は、偽装請負になる可能性も考えられる問題あるやり方です。
◆指定管理料の消費税は4千200万円!
直営の場合、市の運営費のみですが、指定管理の場合、指定管理料に消費税、図書館管理課を置く経費とがかかり、その金額は直営とほぼ同額の約6億円との答弁。一方、指定管理料にかかる消費税は4千200万円との答弁でした。消費税分と(仮)図書館管理課の経費を差し引いた残りの分で指定管理の事業者は業務を行うことになり、サービス向上を含めて運営に不安が残ります。
◆図書館サービス向上計画 比較のデータの数字が違う
指定管理の導入を検討するために市が委託して作成した「豊田市図書館サービス向上計画」の報告書は、(株)図書館総合研究所が作成しました。
この報告書の第1章には、「2013年度の年間貸出数は、173万5,185冊」とあり、「中央図書館以外に交流館分室などが31あり、図書館の分室として貸出しています。サービスポイントと称されている191万9000冊」と、しています。
結局、報告書では、サービスポイントを含まない173万5,185冊が中央図書館の貸し出し数としていますが、比較した他の38中核市の中央図書館の差出冊数はサービスポイントを含む合計数が出ています。明らかに、豊田市の中央図書館と他市の図書館を比較するデータが違っている報告書です。これは研究所のミスとして、承知しているのかとの根本市議の指摘に「中央図書館を目立たせるため出された数字である」ことが答弁されました。次々に重大な問題点が鮮明になる指定管理計画は、凍結・中止しかありません。